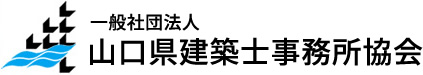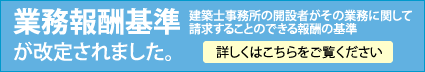設計・工事監理とは
設計
建築士法で、「設計」とは、設計図書を作成することとされています。
設計図書とは建築工事を実施するために必要な図面と仕様書のことです。
この設計図書が適切に作成されていなければ、その設計図書に基づいて行われる建築工事に支障が生じることになります。
良い建物を建てるためには、建築士事務所に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらうことが大切です。ご自分の住まいのイメージや希望などを具体化し、きちんと施工業者に伝わる設計図書を作成してくれる設計者を選びましょう。
工事監理
「工事監理」とは建築主の立場に立って、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。 良い建物を建てるためには、建築士事務所に工事監理を依頼し、適切な工事監理が行われることが大切です。施行不良が原因で生じる欠陥住宅などのトラブルを防止するためにも、建築士の資格を持った専門家がきちんと工事監理を行うことが重要になります。
設計・工事監理を依頼するときの注意点
登録を受けた建築士事務所と契約を
一定規模以上の建築物の設計・工事監理の業務は、都道府県知事の登録を受けた「建築士事務所」でなければ行うことができません。設計・工事監理の業務を依頼しようとする際は、都道府県知事の登録を受けた事業者であることを確認しましょう。
※ 建築士事務所として登録されているかどうかは、事務所に掲示されている標識及び各都道府県の建築士事務所協会(都道府県による指定事務所登録機関でない場合は県)の窓口等で確認できます。
契約前に必ず重要事項説明を受ける
建築士事務所には、設計・工事監理の契約の前に、契約に関する重要事項について書面を交付して説明することが義務づけられています。建築士事務所の建築士からしっかり説明を受けましょう。なお、説明時に建築士は建築士の免許証を提示することとなっています。
書面による契約の締結を
延べ面積300m²を超える建築物については、書面による契約締結が義務化されています。後のトラブル防止のため、委託代金、業務の内容や方法等について合意した上で、記名・押印された書面を相互に交付して契約を締結しましょう。委託代金が適正であるかは、国の定める報酬基準に準拠されているかが、目安になります。
また、「設計」、「工事監理」と「建築工事」をすべて同じ会社と契約するケースでは、すべてを1つの契約書で契約する場合もあります。その際も、「設計」、「工事監理」についての重要事項の説明を受けた上で、必要な事項が書面に記載されていることを忘れずに確認しましょう。
なお、延べ面積300m²以下の建築物については、法律上の義務はありませんが、後のトラブル発生の防止のためにも、書面で契約を締結することをおすすめします。
建築士であることを確認
建築主は、建築士に対して建築士の免許証の提示を求めることが可能で、相手が本当に建築士であるかを確認できます。なお、免許証の携行義務は課されていませんので、携行していない場合は、次回の打合せ時などに見せてもらうようにすると良いでしょう。
なお、建築士免許証には、平成20年以降に交付された力-ド型の免許証明書と、それ以前に交付された紙の免状型の免許証がありますが、どちらも免許証として有効です。
※ 建築士として登録されているかどうかは、各都道府県の建築士会(国及び都道府県による指定登録機関)の窓口等で確認できます。
建築物の設計等の業務を締結する際の新たなルールを定めた改正建築士法が、平成27年6月25日に施行されました。
設計・工事監理の報酬
建築士事務所の業務報酬(設計・工事監理料)は、令和6年国土交通省告示第8号(令和6年1月9日)により標準的な業務報酬基準として算定方法が定められております。
この業務報酬基準は、建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法等を示したものです。業務報酬基準では、建物の用途、面積、業務の難易度等を基に設計業務や工事監理業務の標準的な業務内容と業務量を定めていますので、報酬を決定するときの目安にすることができます。
限られた予算のなかで、建築主にとって良い住環境を創り出すことが設計事務所の仕事です。設計の専門家が充分に時間をかけて設計をし、建築主の立場に立って工事監理をします。